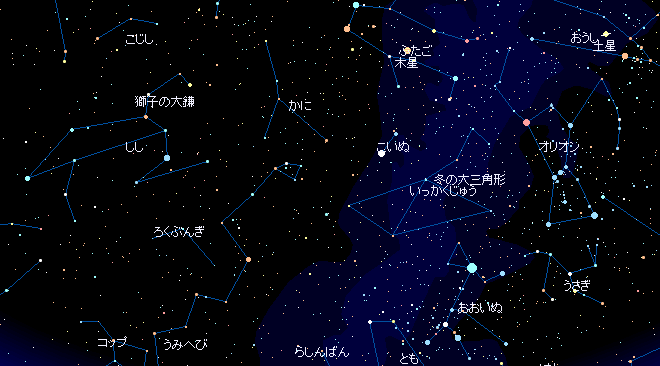
2001年しし座流星群+ちょっと星の勉強
星座はちょっと知っていると、夜空を見る時の楽しみのひとつになってくれます。下の図はしし座流星群が極大期を迎えた2001年11月19日午前3時19分の南東から南の空です。羅針盤、艫(とも)、コップ等耳慣れない星座もありますが、星空がにぎやかな部分で一等星もたくさんあります。さらに木星、土星が冬の星座の中に入っていました。下の写真を見る時、位置を知る参考にして下さい。
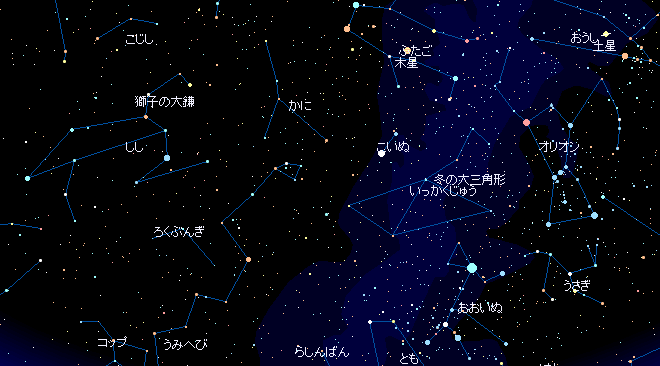
この獅子の大鎌と呼ばれる所から放射状に流星が見られるので、しし座流星群と呼ばれます。下の流星の画像をご覧になる時、獅子の大鎌がどこにあるのかを探してみて下さい。
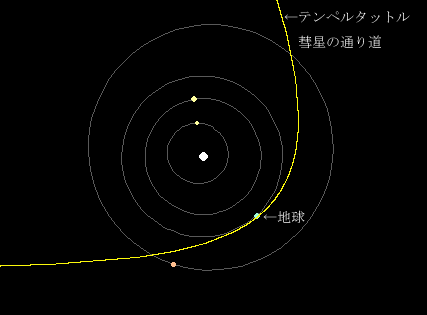 さて、ではどうして獅子の大鎌から星が飛ぶのでしょうか?左の画像はテンペルタットル彗星の軌道と太陽系の火星までの軌道を表しています。
さて、ではどうして獅子の大鎌から星が飛ぶのでしょうか?左の画像はテンペルタットル彗星の軌道と太陽系の火星までの軌道を表しています。
テンペルタットル彗星は33年周期で何度も地球の軌道付近を通過しています。その際、多くの塵を地球軌道付近にばらまいて行きます。その塵のある部分をダストトレイルといいます。
そのダストトレイルの中を地球が通過すると、塵が地球の引力により引きつけられ、大気圏で摩擦熱により燃え尽きます。それが流星群の正体です。
その際、地球はダストトレイルの中、しし座の方向に向かって進むため、見かけ上獅子の大鎌から星が流れるように見えるのです。
テンペルタットル彗星は過去何度も地球軌道付近を通り、たくさんのダストトレイルを残していますが、地球がそこを通過するか否かは、精緻な計算が必要になります。
今回の流星雨はイギリスのデビットアッシャー氏により、1866年のダストトレイルの中を地球が通過することが予測され、見事に的中しました。
上の二枚の画像と下の参考図はいずれもステラシアターと言うソフトを使って作りました。ステラシアターの入手先はこちらです。
 1獅子の大鎌からいくつもの流星が飛んでいます。流星の作る線をたどって交わった所を輻射点(ふくしゃてん)と言い、ここからすべての流星が飛びます。
1獅子の大鎌からいくつもの流星が飛んでいます。流星の作る線をたどって交わった所を輻射点(ふくしゃてん)と言い、ここからすべての流星が飛びます。
輻射点の近くでは観測者に向かって飛んでくるため、短い流星になります。時にはパッと光るだけの点となる流星もあります。輻射点から離れると長い流星が見られます。下の2や3の写真と見比べてみて下さい。
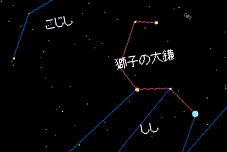
 2獅子の大鎌がどこにあるか解るでしょうか?左にあります。中央上よりの星のかたまりは、かに座のプレセペ星団(M44)といいます。参考図の黄色の円の中です。
2獅子の大鎌がどこにあるか解るでしょうか?左にあります。中央上よりの星のかたまりは、かに座のプレセペ星団(M44)といいます。参考図の黄色の円の中です。
1の画像は50mmレンズですが、この画像は28mmレンズを使っているため、写る範囲が広くなっています。
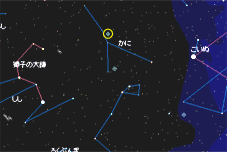

3カラマツ林に隠れようとするオリオン座に流星が降り注いでいます。中央上の明るい星は木星です。では、右よりにあるふたつの明るい星は何でしょう?一番上の星空の画像をご覧下さい。

4中央下のオレンジ色の雲のようなものは流星痕と言われるものです。大きな流星(火球)が飛ぶとこのようにしばらくの間、煙のように夜空を漂う様子が見られます。
これはおおくま座の下の部分です。早い話、北斗七星です。

5流星は肉眼では色がはっきり解らないことが多いのですが、こういう風に写真に撮ると緑やオレンジに輝いているのが解ります。
撮影状況
カメラボディ キャノンA−1 キャノンAE1P
レンズ NFD50mmF1.2 NFD28mmF2.8
フィルム Fuji ネガ 800
露出 いずれも30秒前後
絞り 開放(1、2段絞れば良かったかも)
時刻 2001年11月19日午前3時から4時
いずれもノートリミングの100%画像です。
| 北海道の方言へ | おまけのメニューへ | 壁紙プレゼントへ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
花鳥魚月 |
flyman●octv.ne.jp 巡回ロボットによるメールアドレスサーチ防止のため「@」を「●」に置き換えています。 お手数ですが、コピー&ペーストをしてアドレス中の「●」を「@」に打ち直して送信して下さい。 |